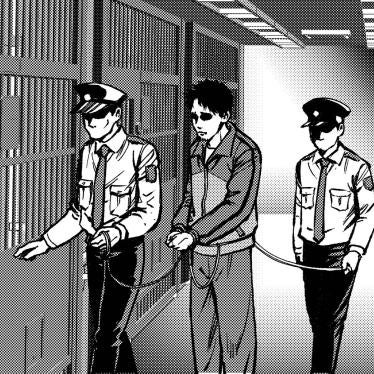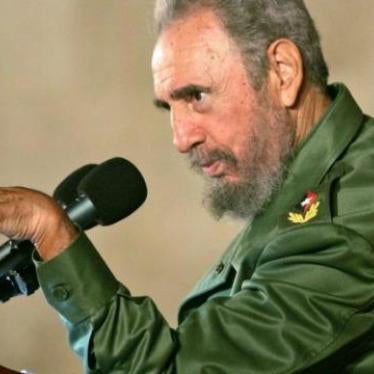(ニューヨーク)インド人民党(BJP)率いる連邦政府は、人権侵害をもたらす外国寄付規制法、ねつ造された容疑による税務調査などの手段を用いて、市民社会団体を不法に攻撃していると、ヒューマン・ライツ・ウォッチは本日述べた。非営利団体に対する外国寄付規制法(FCRA)の恣意的な使用や、非暴力的な政府批判者に対する政治的動機に基づく攻撃は、インドは権利を尊重する民主主義国家であるとの政府の主張をゆるがすものである。
2024年2月2日、インドの捜査機関である中央捜査局(CBI)は、著名な人権活動家であるハルシュ・マンダー氏の自宅と事務所を家宅捜索し、刑事事件として捜査するとした。1月、当局はX(旧Twitter)に対し、マイノリティを被害者とする犯罪を記録するプロジェクト「ヒンドゥトヴァ・ウォッチ」(Hindutva Watch)のアカウントを凍結するよう命じた。当局はまた、ヘイトスピーチ事例を追跡する「インディア・ヘイト・ラボ」(India Hate Lab)のウェブサイトへのアクセスもブロックした。
「活動家団体の動きを封じようとするインド政府の動きからは、政府が基本的権利を著しく侵害している現状が浮き彫りになる」と、ヒューマン・ライツ・ウォッチのアジア局長代理であるミナクシ・ガングリーは述べた。「市民社会に対するインドの攻撃を懸念する関係国政府は、事態がさらに悪化するのを待たず、いますぐ声を上げるべきだ。」
前出のマンダー氏は最近、コミュニティ間の衝突で200人以上が犠牲となったマニプールでの平和行進を主導した。当局による家宅捜索は、ある内務省高官が、マンダー氏が代表を務める研究組織調査団体「公正研究センター」(Centre of Equity Studies)について、外国寄付規制法に関する経理上の不正行為の疑いがあると申し立てたのを受けてのことだ。このほか、アマン・ビラダリ・トラスト、オックスファム・インディア、アクション・エイド・アソシエーションなど、他の非営利団体にも不正の疑いがかけられている。
250人以上の学者、活動家、市民社会のメンバーが、マンダー氏への家宅捜索を「執拗な魔女狩り」と非難した。マンダー氏はヒューマン・ライツ・ウォッチに次のように述べた。「私はこうした攻撃が始まったときから、いや、この攻撃は長いことひたすら続いているのだが、心に決めている。国が私に何をしようとも、私の良心や発言が押し黙ることはないし、私の活動が止むことも決してない」。
2023年6月、インド当局は、公正研究センターの外国寄付規制法の認可証の効力を一時停止していた。マンダー氏が様々な全国紙や独立系出版物に頻繁に寄稿するようになり、同法を違反している疑いがあるというのがその理由だ。
2016年以来、当局は日常的に認可の取り消しや停止を行っており、非営利団体が脱法行為を行っていると非難し、銀行口座を凍結してきた。人権団体は、これは政府が非営利団体を統制する手段の一つだとして懸念している。政府資料によると、2月6日までに内務省は外国寄付規制法の認可証を20,697件取り消した。資金受け取りを禁じられた団体には、人権と民主主義を長年推進してきたところが数多くある。
2月3日には、キリスト教慈善団体のタミル・ナドゥ社会福祉協会が、法律違反を理由に認可証を取り消された。しかし、何が問題だったのかはいまだ不明だ。1月には、政策研究センター(CPR)が、「インドの経済的利益に影響を与える」ための「開発プロジェクトに対する抗議活動や法廷闘争」の資金に外国寄付金を流用したと当局が主張したことで、認可証が取り消された。同センターは声明でこの疑惑を否定し、この動きを「理解しがたく、相当性を欠く」と非難した。
当局はまた、国内で60年以上にわたり、主に貧困地域の子どもたちへの人道支援に力を入れてきたキリスト教慈善団体ワールド・ビジョン・インドの認可証を取り消した。ワールド・ビジョンは声明で「深い失望」を表明し、このような決定は「これから何年もの間、インド全土で脆弱な立場に置かれた多くの人びと」に害を及ぼすことにしかならないだろうと述べた。
ヒンドゥトヴァ・ウォッチとインディア・ヘイト・ラボは、2000年の情報技術法違反の疑いで、国内からアクセスできなくなっている。ジャーナリストやオンラインで政府を批判する人びとは、当局を批判する内容だとの理由で、同法と2021年のIT諸規則で訴追されるリスクが高まっている。前出の2つのプロジェクトを立ち上げたラキブ・ハミード・ナイク(Raqib Hameed Naik)氏は、ヒューマン・ライツ・ウォッチに対し、今回の決定は「極めて憂慮すべきものであり、ヘイトクライムやヘイトスピーチ、偽情報を記録・研究する団体に対して大きな検閲の網がかけられていることを示すもの」であって、「すべての市民の基本的権利である情報アクセス権を直接侵害している」と述べた。
多数派であるヒンドゥー教徒のイデオロギーを推進する人民党政権は、宗教的マイノリティを保護せず、かれらの人権を侵害する政策を採用しており、これまでもそうした人権侵害行為を記録することを取り締まっていた。米国の「国際信教の自由委員会」はこのところ、インドでの宗教的マイノリティに対する攻撃の激化について、複数の声明や報告書を発表している。アムネスティ・インターナショナルは2月7日付の報告書で、超法規的懲罰の一形態として、インド全土でムスリムの家屋だけをねらった解体が広範に行われている現状を広く指摘している。
「インド当局は、宗教的少数派を保護すべく迅速に行動するともに、政府を支持する人びとを含め、暴力的な攻撃を扇動したり、関与したりする者をすべて起訴すべきである」と、前出のガングリー局長代理は述べた。「他の民主主義国との国際的パートナーシップは、すでに悪い状況をさらに悪化させないよう、インドに対して人権施策の軌道修正を行うよう促すべきである」。